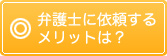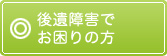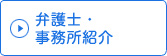後遺障害逸失利益
交通事故による後遺症が、将来に渡ってどれくらいの損失を生じさせるかを計算するための方法です。具体的には、以下のように各項目をそれぞれ確定させて計算していきます。
算定方式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
1. 基礎収入
まず、逸失利益算出の基礎となる収入を決定する必要があります。
基礎収入とは、いわば「交通事故に遭わなかったと仮定した場合に得たであろう収入」のことです。この収入が、交通事故による後遺症を原因として減少した場合、その差額が逸失利益だと考えるわけです。
有職者については原則的に「事故前の現実の収入」を基礎収入と考えます。
ただ実際の生活では、収入というものは将来的に上下する可能性がありますから、その人がどれくらいの収入を得ていくのかを予測するのは中々難しいことです。多分に推定を含む考え方であるため、その方の収入状況によっては基礎収入について争いになることもあります。
2. 労働能力喪失率
等級に応じて、労働能力の喪失率というものが決められます。
交通事故に遭う前の状態に比べ、どれくらい労働能力が失われたかについては、後遺障害等級ごとに定めた目安があります。
| 1級 | 100% | 8級 | 45% |
|---|---|---|---|
| 2級 | 100% | 9級 | 35% |
| 3級 | 100% | 10級 | 27% |
| 4級 | 92% | 11級 | 20% |
| 5級 | 79% | 12級 | 14% |
| 6級 | 67% | 13級 | 9% |
| 7級 | 56% | 14級 | 5% |
たとえば基礎収入が500万円の方について後遺障害等級7級(労働能力喪失率56%)であれば、一年間に失われる利益は500万円×56%=280万円と考えます。
3-1. 労働能力喪失期間を決定
基礎収入と労働能力喪失率が決定したら、この後遺障害を原因とする労働能力喪失が何年間継続するかを考えます。
たとえば手足を切断したり失明したような場合であれば、こうした後遺症は一生残るものですから、症状固定時から就労可能年数の限界(67歳)まで、逸失利益が生じ続けると考えます。
しかし、例えばムチウチなどの場合、通常は労働能力喪失状態が一生続くとは考えず、5年間程度とされることが多いようです。
(例)
後遺障害:両目の失明(1級)、症状固定時の年齢:47歳
→この場合の労働能力喪失期間は、20年間(47歳から67歳まで)
3-2. 将来利息の控除
基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間が決定したら、次に将来利息の控除が行われます。損害額から、将来利息相当額を差引く操作です。
少し分かりにくい部分ですが、逸失利益というのは「将来的にいくらの利益が失われるか」という未来の話をしています。たとえば「労働能力喪失期間が20年、逸失利益が総額1億円」という場合、症状固定から20年先まで生じ続けていく損害を積み重ねると、全部で1億円になるという意味です。
つまり逸失利益が総額1億円だからといって、現在の時点で1億円をそのまま受け取った場合、本来は20年後に得る予定の金額まで含めて前倒しで受け取ってしまうことになります。本来受け取る時期よりも早くお金を受け取るということは、本来受け取る時期までの利息分、もらい過ぎであると考えるわけです。
そこで、損害額から、事前に将来利息分を差し引いた額が被害者に対して支払われることになります。
この計算方法は「ライプニッツ式」「ホフマン式」といったものがあり、一覧表化されたものが係数表として利用されています。例えばライプニッツ係数を用いる場合、以下のようにして逸失利益の計算を行います。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
|---|---|
| 1年 | 0.9524 |
| 2年 | 1.8594 |
| 3年 | 2.7232 |
| 4年 | 3.5460 |
| 5年 | 4.3295 |
| 6年 | 5.0757 |
| 7年 | 5.7864 |
| 8年 | 6.4632 |
| 9年 | 7.1078 |
| 10年 | 7.7217 |
| 11年 | 8.3064 |
| 12年 | 8.8633 |
| 13年 | 9.3936 |
具体的な計算方法の例
(例)
- 基礎収入:年収500万
- 後遺障害等級:5級(労働能力喪失率79%)
- 労働能力喪失期間:10年(これに対応するライプニッツ係数は7.7217)
→逸失利益は、500万×79%×7.7217=3050万0715円
労働能力喪失期間に応じた個所の係数を、「基礎収入×労働能力喪失率」に掛けることで、将来利息を控除した「現在受け取ることのできる額」が算出されるというわけです。